【絆を深める脳内物質】愛情ホルモン・オキシトシンの効果と役割
今回は、愛情ホルモンと呼ばれる「 オキシトシン 」の効果と役割についてわかりやすく解説していきます。

オキシトシンってどんな効果があるんだろう?

愛情ホルモンと呼ばれていますが、具体的にどんな効果があるのか見ていきましょう!
◆この記事でわかること
- オキシトシンの役割
- オキシトシンの機能
- オキシトシンの仕組み
- 多いときと少ないときの影響
- オキシトシンを増やす活動
◇こんな方におすすめ
- 出産の予定がある人
- 親子や恋人、友人など、人との絆を増やしたい人
- 出産を控えた女性の方
オキシトシンの効果と役割
まずは、オキシトシンの基本的な効果と役割について見ていきましょう。
オキシトシンは脳の視床下部の神経細胞で産生される神経ペプチドの一種で、出産や授乳、子育てや他個体との関わり合いなどで脳内および血中へ放出されることから、“愛情ホルモン”や“信頼ホルモン”とも呼ばれています。脳内に放出されたオキシトシンは、さまざまな脳領域の活動に影響を与えて、生物の行動を変化させる作用が知られています。
「“愛情ホルモン”オキシトシンが脂肪を燃やすための脳の神経路を発見~情動–自律神経連関のメカニズム解明や新たな肥満治療法の開発に可能性~」より引用
オキシトシンの役割
オキシトシンは、身体的な結合や社会的な行動に関与するホルモンです。特に出産時の子宮収縮や乳汁分泌に関与し、親子の絆や信頼関係の形成、社会的な絆の構築に重要な役割を果たしています。
具体的な機能、作用
オキシトシンの主な機能は、陣痛を正常に引き起こし、出産を助ける作用です。
また、授乳時には乳汁分泌を促進します。さらに、オキシトシンは「信頼や愛情の感情を高める効果」もあり、親子の絆を強めることや、パートナーや友人との信頼関係を構築するのにも関与しています。
オキシトシンのメリット
オキシトシンは、出産や授乳、感情の調節、社会的な絆の形成などに重要な役割を果たすため、親子の絆や信頼関係の形成にメリットがあります。
また、オキシトシンの放出は、リラックスやストレス緩和にも寄与します。
なので、人間関係のストレスが多い方は特にオキシトシンを増やしていくことがおすすめです。
オキシトシンの効果
オキシトシンは、身体的および精神的な側面でさまざまな効果を持つホルモンです。具体的な効果は次の通りです。
- 子宮収縮: 出産時の子宮収縮を促進、子宮口の開きを助け、出産の進行を支援する効果がある
- 授乳: 母乳分泌を増加させ、授乳時に母子の絆を強める助けとなる
- 食欲の抑制:オキシトシンは食欲を抑制し、体重のコントロールや健康的な食事習慣の促進に寄与する
- ストレス軽減:オキシトシンはストレスを軽減し、リラックス効果をもたらす(例えば、抱擁や親子のスキンシップなど、身体的な接触がオキシトシンの分泌を促進する)
- ストレスホルモンの抑制:オキシトシンはストレスホルモンであるコルチゾールの分泌を抑制し、ストレスに対する身体的および心理的な反応を軽減します。
- ストレス耐性:ストレスに対する心理的耐性を高め、社会的支援の存在によるストレスの緩和を助ける効果がある
- 心理的な幸福感:オキシトシンの増加は、心理的な幸福感や満足感をもたらし、ストレスや不安の軽減につながる
- 自己癒着:オキシトシンは、心理的な傷やトラウマの克服に役立ち、自己癒着や心の安定に寄与する効果がある
- 自己認識:オキシトシンは他者との関係をよりポジティブに認識し、自己肯定感や自己価値感を向上させる
- 記憶と学習:記憶と学習を向上させることが示唆されており、特に社会的な情報や経験の記憶に関連している
- 認知機能の向上:オキシトシンは認知機能を向上させ、注意力や集中力を高める可能性もある
- 対処能力の向上:オキシトシンは対処能力を向上させ、困難な状況に対処する能力を高める
- 傷の癒着:オキシトシンには傷の癒着を促進し、傷口の治癒を助ける効果もある
- 性的興奮:オキシトシンは性的興奮を高める可能性があり、特に親密なパートナーシップや性的な経験に関連している。
- 社会的行動の規範:オキシトシンは、社会的行動の規範や倫理観の形成にも関与し、他者との関係を維持する上で重要な役割を果たす
- 社会的な信頼:オキシトシンは社会的な信頼感を高め、他者との協力や共同作業を促進する
- 対人行動の向上:オキシトシンは、他者に対する思いやりや共感心を高め、対人関係における積極的な行動を促進する
- 対抗的行動の抑制:オキシトシンは攻撃的な行動や敵対的な態度を抑制し、対人関係における平和な交流を促進する効果がある
- 社会的結合:オキシトシンは信頼感や社会的結合を促進し、親子関係や友情、ロマンチックなパートナーシップの形成に重要な役割を果たす
- 慈愛と親密さ:オキシトシンは慈愛や親密さを促進し、愛情深い関係や絆の形成を助ける効果がある
オキシトシンの注意点
次に、オキシトシンにおける注意点についても見ていきましょう。
多すぎるとどうなるか?
オキシトシンの過剰分泌は、陣痛の強さや子宮収縮を引き起こす可能性があります。また、一部の研究では、高レベルのオキシトシンがソーシャルアンキシエティ(社交不安)を引き起こす可能性も示唆されています。
少なすぎるとどうなるか?
オキシトシンの不足は、出産時の陣痛や乳汁分泌の困難を引き起こす可能性があります。また、親子の絆や社会的な関係の形成にも影響を及ぼす可能性があるので注意が必要です。
オキシトシンが増える行動
オキシトシンの放出は、身体的な接触、愛情の表現、視覚的な刺激、タッチ、マッサージ、優しい言葉や声の使用などによって促進されます。
つまり、オキシトシンを増やす行動を増やしたいなら、パートナーとのスキンシップ、子どもとの親しい関係の構築、友人とのコミュニケーションなどを増やしていきましょう。
オキシトシンを増やす具体的な行動は以下の通りです。
これらの行動は、オキシトシンの分泌を促進し、結果として愛情、信頼、安心感などのポジティブな感情を高める効果があります。
オキシトシンの仕組み、特徴
オキシトシンは、「脳下垂体後葉」から放出され、血液中に循環します。
オキシトシンを分泌する主な刺激は、分娩の進行や授乳、身体的接触、愛情表現などです。
大きな特徴としては、感情のコントロールや社会的な行動に関与することで知られており、ストレス緩和やリラックスにも効果があります。
オキシトシンに関する有名な実験例
ペアボンディング(Pair bonding)は、動物行動学や社会心理学などの分野で使用される概念です。この用語は、特定の個体同士が密接な関係を築く行動やプロセスを指します。一般的に、ペアボンディングは以下のような状況で見られます。
- 親子の絆: 親と子供の間には、親子の絆が形成されます。これは、子供が生後すぐから親に対して感じる信頼や安全な関係を指します。
- ロマンチックな関係: パートナーシップやロマンチックな関係においても、ペアボンディングが発生します。これは、お互いに対する愛情や信頼、絆が築かれるプロセスを指します。
- 友情: 友人や仲間との間にも、ペアボンディングが存在します。共通の興味や価値観、経験に基づいて、強い絆が形成されることがあります。
- 同僚関係: 職場や学校などでの同僚関係においても、ペアボンディングが発生することがあります。共同の目標や仕事の性質によって、チームメンバー同士が絆を深めることがあります。
「ペアボンディング」は、集団内の個々の関係が強化され、社会的な結束力や個体の幸福感を高めるのに役立ちます。この概念は、生物学的な親子関係から、社会的なパートナーシップや友情まで、さまざまな人間関係の形成に関連しています。
《オキシトシンに関するその他の実験》
- 親子の絆とオキシトシン: この実験では、母親と赤ちゃんの間の親子の絆とオキシトシンの関連性が調査されました。母親と赤ちゃんがスキンシップを行ったり、眼を見つめ合ったりすることで、オキシトシンの分泌が増加し、親子の絆が深まることが示唆されています。
- 信頼と社会的行動とオキシトシン: この実験では、オキシトシンが社会的な信頼感や協力行動にどのように影響するかが調査されました。参加者にオキシトシンまたはプラセボが投与され、信頼ゲームや社会的なシナリオを通じて、オキシトシンの影響が評価されています。
- ストレスとオキシトシン: ストレス状態下でのオキシトシンの効果に関する実験も行われています。ストレスフルな状況でオキシトシンが投与され、ストレス反応の軽減やストレス耐性の向上が評価されました。
- 自閉症スペクトラム障害(ASD)とオキシトシン: ASDの治療や症状の管理に関する研究では、オキシトシンの効果が評価されています。特に、オキシトシンが社会的なコミュニケーションや相互作用の改善にどのように寄与するかが焦点となり、研究が進められています。
これらの実験を通じて、オキシトシンが人間の行動や社会的な相互作用に与える影響がより深く理解され、心理学や神経科学の分野でさまざまな応用が期待されています。
愛情ホルモン・オキシトシンの効果と役割【まとめ】
オキシトシンは親子や恋人関係だけでなく、人と人との繋がり全般、社会的な繋がりにも影響を与えていること。
・オキシトシンは感情の調整にも使われていること
・多すぎても、社会不安を引き起こす原因になること
・出産や授乳、陣痛の強さにも影響があるホルモンであること
・集中力や注意力を高める効果もあること
・傷の治りが早くなること
ストレス耐性を高め攻撃的な行動や態度を抑制して対人関係を円滑にするのに役立つこと
《関連記事》
「ホルモン」に関しては、こちらの記事もおすすめです。
【多幸感UP】快感ホルモン『 エンドルフィン 』の機能と高め方
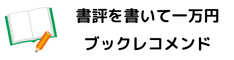
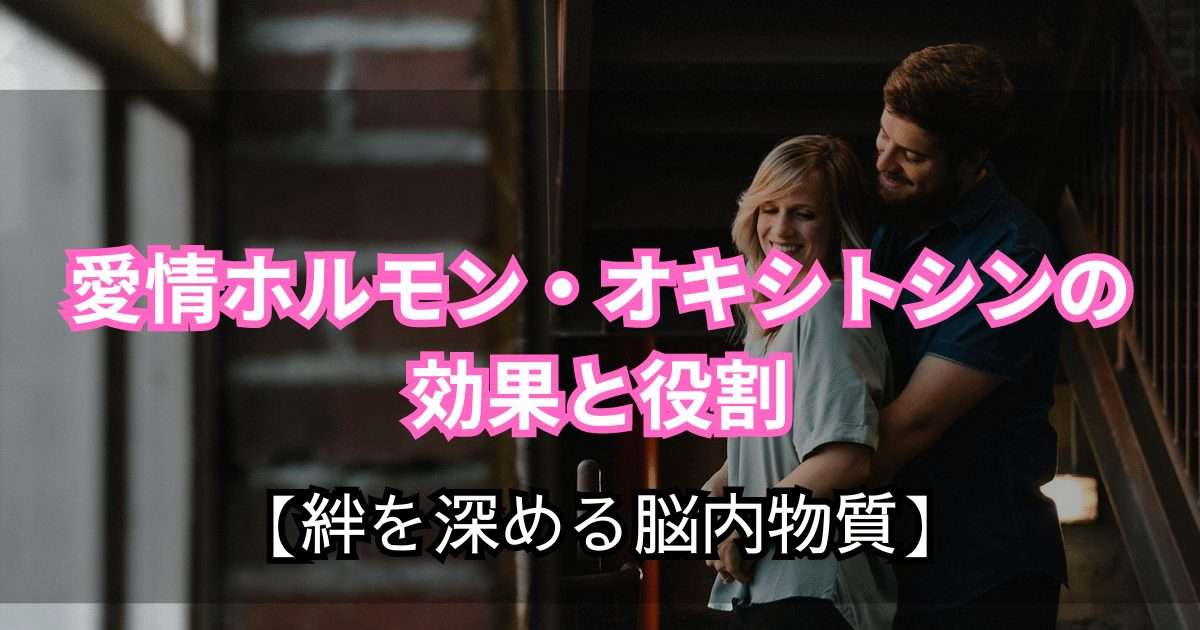

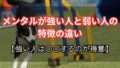

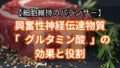
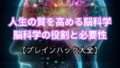



コメント