【安眠を手に入れよく朝スッキリ】睡眠の質を高める50の方法
今回は、「 睡眠の質 を上げる方法 」について解説していきます。

最近、ぐっすり眠れている気がしない・・
誰か改善方法を教えてく..daさ、、iZzzzz・・・

まずは良質な睡眠の仕組みから理解していきましょう!
◆この記事でわかること
- 睡眠の質が悪いと起こるデメリット
- 睡眠の質を上げるポイント
- 睡眠の質を上げる方法
◇こんな方におすすめ
- いつも寝ているのに寝足りないと感じている人
- よく朝スッキリ目覚めたい人
- 次の日に疲れを残したくない人
- 睡眠の質を上げたい人
>>日中のつらい 眠気 を防ぐ方法【覚醒力と睡眠欲求】
睡眠の質 が悪いとどうなるのか?

睡眠には「精神&身体疲労の回復」「免疫機能の増加」「細胞の修復」「記憶の整理と定着」「感情の整理」「精神機能の回復」など、休息に関する様々な働きがあります。
長い間、睡眠の質が低下することによって休息がうまくいかなくなると、心身に様々な悪影響を及ぼす原因になるので注意が必要です。
1、精神機能の低下を引き起こす
「精神機能」とは、注意、認知、記憶、感情、意欲など精神活動に関わる機能のことです。
睡眠の質が低いことによって、様々な精神機能に悪影響が出ます。
要は、睡眠の質が悪くなることで、頭がうまく回らなくなったり、気力が下がったりなどの精神的な不調に陥りやすくなります。
2、気分が沈みやすくなる
睡眠の質の低下によってストレス処理がうまくいかなくなることで、落ち込みやすくなります。
また、うつ病などの精神疾患にもなりやすくなるなど、睡眠の質の低下は、心の健康にも大きな悪影響をもたらす原因にもなります。
3、様々な病気のリスクが高まる
睡眠の質が低い状態が長く続くと病気、または身体機能の不調に陥りやすくなるので、注意が必要です。
睡眠の質 を上げるポイント

睡眠の質を上げるポイントは、主に以下の4つです。
この4つを意識して改善するだけで、睡眠の質を一気に上げることができます。
- 副交感神経
- 深部体温
- メラトニン
- 体内時計
1、副交感神経を優位にさせる
自律神経とは、簡単にいうと自分の意思に関わらずに自動的に働く神経のことで、心臓や肝臓などの内蔵や器管を動かしている神経です。
脳から命令を出さなくとも無意識に呼吸を続けたり、心臓を動かし続けたり、食事をしたら自動的に食べ物を消化したりできるのは自律神経の働きによるものです。
主に身体のパフォーマンスに大きく関わる自律神経には、交感神経と副交感神経があります。
睡眠の質を上げるためには、当然ながら交感神経(活動モード)よりも副交感神経(休息モード)が優位になっていることが大切です。
2、深部体温を高める
パソコンなどの機械と同じで、起きている間は精神活動によって脳神経を使い続けていくうちに、脳の温度はどんどん上がっていきます。そして、脳の神経を消耗していきます。
脳の温度が高いと脳の神経が休まらないので、脳の神経の消耗を回復するためにはこの脳の温度が下がっている必要があります。
つまり、睡眠により脳の温度を下げることで脳の神経の活動を抑えることによって、脳が休息しやすい状態にさせているのです。
また、脳にある「温度を感知するセンサー」と「睡眠中枢」が隣接しているため、体温と睡眠には密接な繋がりがあるとも言われています。
要は、高い深部体温を下げることによって睡眠の準備を整えた合図として眠気が起こるので、深部体温を上げることで寝付きをよくすることがでるという仕組みです。
深部体温を上げる→体温を戻そうとして放熱する→深部体温が下がる過程で脳の温度も下がっていく→脳が眠る準備ができたと認識して眠気が起こる→スムーズに眠れるようになる
なんか、深部体温と眠気の関係って「風が吹けば桶屋が儲かる」みたいな構図ですね(笑)
3、「メラトニン」の分泌を安定させる
「メラトニン」が適度に分泌されている状態で眠ることで、細胞の修復や免疫の増加など、睡眠の休息効率がよくなります。つまり、メラトニンによって睡眠の質が上がりるというわけです。
4、体内時計を整える
夜更かしや徹夜、長時間の昼寝などにより睡眠の時間がバラバラになり体内時計が狂うと、睡眠サイクルも乱れて睡眠の質にも大きく悪影響がでてきます。
日中眠気に襲われることなく活動でき、夜に自然に眠れるようになるためには、体内時計が整っていることが大切です。
睡眠の質 を高める方法 50選

さて、それではいよいよ、睡眠の質を上げる方法を紹介していこうと思います。
数多くあげるので、いろいろ試してみて、自分に合った方法を見つけてみてください。
副交感神経を優位にさせリラックス効果を得る
- マッサージ
- 不安やストレスの原因を紙に書き出す
- 就寝前の糖質制限
- 瞑想
- 10・20呼吸法
- ビタミンB1
- アロマテラピー
- 自然音
- 1/fの揺らぎの音楽
- ストーリー系の読書
- 散歩
- カフェイン制限
- カモミールティー
1、寝る前にマッサージなどで筋肉をほぐす
→筋肉をほぐすことで副交感神経が優位になりリラックス効果を得られる。ゆったり湯船に浸かりながらやるとさらに効果的。
2、不安やストレスの原因を紙にすべて書き出す
→ストレスは交感神経を刺激し、脳を興奮状態にさせ眠りが浅くなる原因にもなる。睡眠の質を上げるためにはストレスや不安対策をすることで、交感神経の高ぶりを抑えることが大切。
不安やストレスの原因を紙に書き出すだけでストレス値が減少することが様々な研究でわかっており、寝る前のストレス対策におすすめ。「紙に書き出すことによって視覚的に文章として認識すること」がポイント。
3、寝る前の糖質を控える
→糖質をとりすぎると、血糖値が乱れやすくなり、血糖値が乱高下することによって交感神経が刺激される。なので、寝る前に糖質を大量にとるのは、結果的に睡眠の質の低下につながるので注意。
4、瞑想
→呼吸を整えることで自律神経も整えることができる。
吸う息を長くすると交感神経が優位になり、吐く息を長くすると副交感神経が優位になる。なので、寝る前の呼吸瞑想は、吸う息よりも吐く息を長めにすることがポイント。
5、「10・20呼吸法」
→10秒かけて鼻から息を吸い、20秒かけて息を吐くを交互に繰り返す(鼻から息を吐くのが難しい場合は吐く息は口からでもOK)。
口呼吸よりも鼻呼吸の方が自律神経が整いやすい。
6、ビタミンB1をとる
→ビタミンB1には、イライラや不安、ストレスの軽減、疲労回復効果がある。豚肉、ゴマ、大豆製品に多く含まれている。
7、安眠効果の高いアロマをかぐ
→ラベンダー、ベルガモット、スイートオレンジ、カモミール、サンダルウッド、イランイランなどが高いリラックス効果と安眠効果が期待できる。
8、寝る前に自然音を流す
→自然界の音は「1/fのゆらぎ」と呼ばれる特殊な周波数をもっていることが多く、この周波数の音を聴くことによって脳波がアルファ波の状態になりやすくなる。
波の打ち返す音、雨の音、風で木々の葉がそよぐ音、川の水流の音などがこの周波数である場合が多い。また、赤ちゃんが聞くと泣き止むと言われているピンクノイズもこの周波数を持っている。
ちなみに、「1/fのゆらぎ」には光の周波数にも当てはまり、焚き火の火の揺らぎに含まれる光の周波数は「1/fのゆらぎ」になっている。火のゆらぎを見ていてどことなく落ち着くのは、この周波数の効果とも言える。
9、「1/fのゆらぎ」の音楽を聴く
→バッハやモーツァルトなどのクラシック音楽に多い。また、ポップスでは宇多田ヒカル、吉田美和、MISIA、藤原聡、松任谷由実、中島美嘉、美空ひばりなどが「1/fのゆらぎ」の声を持つと言われている。
10、寝る前にストーリー系の本を読む
→寝る前の読書にはストレス発散効果があり、メンタルを安定させる効果がある。メンタルが安定した状態で寝ることで睡眠の質も高まる。
頭を使うハウツーより、没入感のあるフィクション系の本がおすすめ。現実から思考を切り離すことによってストレスが発散しやすくなるという仕組み。
ゲームなども当てはまりそうではあるが、寝る直前の脳には刺激が強すぎるためおすすめしない。
11、散歩
→散歩をすることでリラックス効果を得ることができる。
リラックスしているとき、脳は寝ているときの脳波(シータ波)に近い「アルファ波」の状態になり、入眠しやすくなる。
12、夕方以後はカフェインをとらない
→カフェインには覚醒作用の他にも副交感神経の働きを鈍くさせる効果がある。
カフェインが体内から抜けるまで個人差はあるが、だいたい6〜9時間かかると言われている。なので、24時までに寝るのであればカフェインは15時以後はとらない方が無難。
13、カモミールティーを飲む
→カモミールのアロマには高いリラックス効果がある。また、ノンカフェインなので覚醒作用がないので寝る前にぴったり。
深部体温を高める
- 白湯
- 生姜湯
- 夕食後の運動
- 手足の血行促進
- 湯船でストレッチ
- 目元を温める
- 靴下を脱いで寝る
- ぬるま湯にゆっくり浸かる
- カプサイシン(香辛料)を避けた晩飯
- パジャマに着替える
- 通気性の良い寝具
- 自分に合った高さの枕
- 最適な室温と湿度
- 筋弛緩法ストレッチ
14、白湯を飲む
→胃から内蔵を温めることによって深部体温を高めることができる。白湯は胃に負担がかかりにくく、またリラックス効果もあるのでおすすめ。
15、生姜湯を飲む
→生姜湯には深部体温を高める効果がある。また、冷え性の改善にも効果的。
16、夕食後に軽く運動をする
→運動で血流が増えることによって脳の温度も上昇する。そして寝る直前までに徐々に血流と共に体温も下がっていくので、寝る頃には寝付きがよい状態になりやすくなる。
ただし、激しい運動は交感神経を刺激するのでNG。
少し速歩きのウォーキングなど軽めの運動がおすすめ。
17、手足の血行をよくする
→手足の末梢血管が拡がることによって放熱性がよくなり、深部体温が下がりやすくなる。
18、湯船でストレッチ
→毛細血管が拡がりやすくなることによって、風呂上がりに深部体温が下がりやすくなる。
19、目元を温める
→頭(おでこ付近)からの放熱により、脳の温度も下がりやすくなる。またおでこ周りの筋肉もほぐれることで、高いリラックス効果も得ることができる。
20、靴下は脱いで寝る
→靴下を履いたままの状態では足から放熱しにくくなるので、深部体温も下がりにくくなる。深部体温が下がらないと神経が休息しづらくなるのでNG。
21、ぬるま湯にゆったり浸かる
→お湯の温度は38〜40度ぐらいがおすすめ。ゆったり浸かることで末端血管も拡がり、熱放散がしやすくなる。
逆に41度以上の熱めのお湯は交感神経を刺激するので、安眠にはNG。
22、遅めの晩飯にはカプサイシン(唐辛子)入りの料理は避ける
→カプサイシンの高い保温効果で深部体温が下がりにくくなる。食べるのであれば、就寝と食事は3時間以上間隔を空ける必要がある。
23、パジャマに着替えてから寝る
→パジャマには通気性のいいものが多く、熱放散の効率が高い。また、軽量で摩擦が少ないので、寝ている間の身体の負担も少なくできる。
さらにパジャマに着替えてから寝ることを習慣にすることによって、パジャマに着替える=寝る準備、と脳が認識することでそれが心理的スイッチになり、自然に眠れるようになる。
24、吸湿性や放湿性、通気性のよい寝具を使う
→布団の中の湿度が高いと、寝ている間の温度調節がうまくいかなくなり、寝苦しさの原因になる。
よく汗を吸い、発散させる機能が高い寝具を選ぶのが大切。
25、自分に合った高さの枕を使う
枕の高さが合っていないと、首周りの筋肉が緊張した状態で眠ることになり、睡眠の質が下がる原因になる。
枕を買い替える前に、今ある枕でタオルを使って高さ調節しながら、ちょうどいい高さを調べるのがおすすめ。
仰向けの状態から寝返りがしやすい高さを選ぶのが理想的。
26、寝室の温度と湿度を快適に保つ
・室温→夏:26度前後、冬:20度前後
・湿度→40〜70%がおすすめ。
27、筋弛緩法ストレッチ
→10秒間思い切り全身の筋肉に力を入れて、一気に脱力する、を数回繰り返す。
力みからの脱力によって筋肉がほぐれ、筋肉の血管が収縮することによって血行がよくなり、放熱性も上り、高いリラックス効果を得ることができる。
睡眠ホルモン(メラトニン)の分泌を安定させる
- 朝の日光浴
- トリプトファン
- タンパク質多めの夕食
- 朝食に乳製品(トリプトファン)
- GABA
- テアニン
- マグネシウム
- グリシン
- ナイアシン
- クロセチン
- 乳酸菌
- 夕食と就寝時間の間隔を開ける
- 就寝前のアルコール制限
- 就寝前の喫煙制限
- 就寝前のブルーライト制限
- リラックスタイムに笑う習慣
- 横向きに寝る
- 歯磨きは寝る1時間前に終わらせる
28、朝は太陽の光をたっぷり浴びる
→睡眠の質を大幅に上げるには睡眠ホルモンと呼ばれる「メラトニン」が不可欠。そのメラトニンの素になっているのが「セロトニン」であり、セロトニンは太陽の光を浴びることで生成される。
つまり、朝にセロトニンを分泌させることで、夜にはメラトニンの多い状態で眠れるようになる。
29、トリプトファンを多くとる
→トリプトファンはセロトニンやメラトニンの素になる。
大豆製品、カツオ、マグロ、卵、乳製品、牛肉、バナナなどに多く含まれている。
トリプトファンはビタミンB6(肉類、青魚など)といっしょにとると吸収効率がよくなる。
30、夕食はタンパク質が多めの食事をとる
→タンパク質は寝ている間の細胞修復の材料になる。材料が少ないと当然ながら細胞の修復効率も下がりやすくなる。
31、朝食に乳製品(トリプトファン)をとる
→セロトニンの素になるトリプトファンの多く含まれる乳製品を朝にとることによってセロトニンが生成されやすくなり、夜にメラトニンも多く分泌されやすくなる。
※朝に乳製品をとる人は、起床時間が早く、日中の眠気が少なく、睡眠時間が短い傾向にあることが明らかになっている。また、鬱にもなりにくいという調査結果もある。
32、眠る30〜60分前にGABAをとる
→GABAには、神経への沈静作用があり、興奮を抑えて寝付きをよくする効果がある。また、ストレスを減少させる効果もあり、寝る前にGABAとることで安眠できるようになる。
GABAをとることでノンレム睡眠の割合が増えることも確認されている。
※ノンレム睡眠・・人は寝ている間に深い寝りであるノンレム睡眠と、浅い寝りであるレム睡眠を90分周期で繰り返している。深い寝りのときに精神機能の回復や細胞の修復が行われているので、睡眠の質を上げるにはどれだけノンレム睡眠をしっかりとれるかが重要になってくる。
33、テアニンをとる
→テアニンには気持ちを落ち着かせる効果があり、寝る前にとることで睡眠の質を上げることができる。
テアニンは、緑茶や紅茶に多く含まれている。
34、マグネシウムをとる
→マグネシウムには、筋肉のリラックス、不安の軽減、GABAの効果を向上させる効果がある。寝る前にマグネシウムをとることによって鬱予防にもなる。
アーモンド、ピーナッツバター、ほうれん草、豆乳に多く含まれており、前者ほどではないが乳製品、バナナなどからもマグネシウムはとることができる。
35、グリシンをとる
→グリシンには、日中の眠気や疲労感を改善させる効果がある。グリシンをとり続けることによって、統合失調症や脳卒中のリスクも下がることがわかっている。
ホタテ、鶏もも肉、カツオなどに多く含まれている。
※統合失調症・・幻覚や幻聴、被害妄想、感情表現や認知機能、意欲の低下など様々な精神機能の異常がもたらされた疾患のこと。異常な行動や支離滅裂な言動(言葉がまとまらない)も多くなり、不安や孤独感も増大しやすくなる傾向にもある。
36、ナイアシンをとる
→不安を抑え、寝付きをよくする効果がある。また、鬱病のリスクも下げることができる。
鶏むね肉、カツオ、たら、マグロ、レバー、きのこ類に多く含まれている。
37、クロセチンをとる
→中途覚醒の頻度の減少や肉体疲労の回復、起床時の眠気が残りにくくなる効果がある。また、眼精疲労の回復や細胞の酸化を防ぐ抗酸化作用もある。
クチナシの果実や、サフランからとることが可能。サプリメントがおすすめ。
38、乳酸菌をとる
→乳酸菌をとることにより腸内環境が整うことでセロトニンが分泌され、リラックスした状態で眠りにつきやすくなる。また、乳酸菌をとることで、熟睡時の睡眠であるノンレム睡眠が長くなるというデータもある。
39、夕食は寝る3時間前までに終わらせる
→食べること、特に「味覚」を使うことによって覚醒ホルモンである「オレキシン」が分泌される。このオレキシンが分泌されている状態だと疲労回復に一番重要であるノンレム睡眠に入りづらくなる。なので、オレキシンがなくなってきたタイミングで眠るのがベター。夕食から就寝までは2〜3時間は空けたいところ。
40、寝る前のアルコールは控える
→アルコールは肝臓によってアセトアルデヒドに分解されます。アセトアルデヒドは睡眠の質を下げ眠りを浅くして、中途覚醒の原因になるので、寝酒は控えた方が安眠につながります。
41、寝る前の喫煙は控える
→ニコチンには覚醒作用があるため、寝る直前に吸うと睡眠の質が低下しやすくなる。
42、寝る前のブルーライトは避ける
→ブルーライトを浴びると、睡眠の質に大きく関わるホルモンである「メラトニン」の量が抑制される。本来なら寝る前はスマホやパソコン、TVなどは避けたほうが睡眠の質にはいいが、どうしても見たい場合はブルーライトカットメガネ等を使うのがおすすめ。
43、帰宅後お笑い動画を見る(リラックスタイムに笑う習慣を作る)
→笑うことで「セロトニン」が出やすくなり、リラックス効果が高まる。夜のリラックスタイムで笑う習慣を身につけておくとストレス発散にもなり睡眠の質が上がりやすくなるのでおすすめ。
44、横向きに寝る
→仰向けに寝るよりも横向きに寝た方が、「脳の老廃物」と呼ばれ、認知症の原因になるとも言われているアミロイドβが排出されやすくなる。
45、歯磨きは寝る1時間前までには終わらせる
→歯磨き粉の成分には覚醒作用のあるメントールが含まれていることが多い。就寝の3時間前に早めに夕食をとり、その直後に歯を磨くようにすれば間食も防げるのでおすすめ。
体内時計を整える
- 寝起きすぐの日光浴
- 寝る時間と起きる時間の固定
- 照明の色調(温度感)の調整
- 昼寝は15~20分まで
- 二度寝の回避
46、寝起きすぐにカーテンを開ける
→人間の体内時計は約24時間10分前後と言われており、1日の時間と若干ズレているそうだ。(季節によって変化していく日照時間に対応するためだと言われている)
通常、人間は太陽が出ている間に活動して、太陽が沈む頃に休息する生き物なので、太陽の光を浴びることによって体内時計をリセットし、活動する時間を認識している。
(例えば、太陽の光が全く入らない部屋に数週間居続けると体内時計がどんどんズレていく)
なので、体内時計を正常に保つためには太陽の光を朝に浴びて朝であることを体に認識させる必要がある。
47、寝る時間と起きる時間を固定する
→本来であれば体内時計に合わせて自然に起きて自然に眠りにつくのが理想ではあるが、夜中も明かりをつけて活動できる現代社会では、ついつい夜更かしや徹夜などで1日のリズムが狂いがちに。
1日のリズムが狂うと、体内時計が乱れ睡眠のリズムにも悪影響がでるので注意が必要。
眠る時間を固定するなら、特に起きる時間を固定すると眠る時間が限られてくるため、夜自然に眠りやすくなるのでおすすめ。
48、昼間は昼光色、夜間は暖色系の明かりを使う
→昼光色には昼の青空と同じ光の波が含まれている。つまり、夜に昼光色の明かりを浴びると、まだ昼間だと身体が勘違いしやすくなるため夜間は点けない方がベター。
逆に、昼間に室内にずっといる場合は、身体に活動時間だと知らせるためにも昼光色やブルーライトはガンガン浴びた方がいい。
49、昼寝は15時までで20分以内にする
日中は「覚醒力」が「睡眠欲求」を抑えることで活動できており、睡眠欲求は起きている間中に上り続け、睡眠欲求が覚醒力を上回ることで眠気が起こるようになっている。
昼間に寝すぎると、睡眠欲求が下がりすぎて夜に眠気が足りなくなり、寝付きが悪くなりやすくなるので注意。
50、二度寝をしない
→二度寝をすると、覚醒のタイミングがズレて体内時計も狂いやすくなるので、決まった時間にいつも起きられるようにすることが大切。二度寝をしなければ眠気が取れないようであれば就寝時間を早めて睡眠時間を長くする必要がある。
睡眠の質を上げる方法TOP4
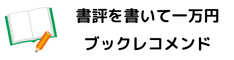


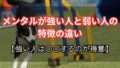

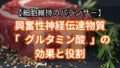
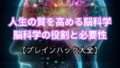



コメント