今回は、「 日中 の 眠気 」の原因と対策についてわかりやすく解説していきます

日中、やることがあるのに眠気のせいで集中できなくなったら最悪ですね。 かくいう私も日頃の不摂生からか、「寝ても寝ても眠い」という現象に悩む時期がありました。
なぜ、日中 眠気がくるのでしょうか。今回はその原因をはっきりさせ、改善できる方法がないかリサーチしていきました。
やるべき作業があるのに、日中の眠気に襲われやすくて全然作業が捗らない! と困っている方の参考になれば幸いです。
それでは見ていきましょう。
◆この記事でわかること
- 眠気のメカニズム
- 覚醒力と睡眠欲求の関係
- オレキシンの効果
- 体内時計を整える方法
- 鉄不足と眠気の関係性
- 交感神経を優位にさせる方法
◇こんな方におすすめ
- 日中ひどい眠気に襲われやすい人
- 日中の眠気を取り除く方法を知りたい人
- 寝ても寝ても寝足りない人
睡眠に関しては、こちらの記事もおすすめです。 「睡眠の質 を上げる方法 50選【睡眠改善】」
眠気 はなぜ起こるのか?
まずは眠気が起こる根本的な原因を見ていきましょう
眠気 のメカニズム
睡眠に関わる機能には「睡眠欲求」と「覚醒力」があります。 この2つのバランスによって「眠気」の強さが変わり、睡眠欲求が覚醒力を上回ることで眠気が起こる仕組みです。
そして、この2つのバランス整えているのが「体内時計」です。
 画像出典:眠りのメカニズム|e−ヘルスネット
画像出典:眠りのメカニズム|e−ヘルスネット
第一のシステムは、覚醒中の疲労蓄積による睡眠欲求(青矢印)です。睡眠欲求は目覚めている時間が長いほど強くなります。徹夜などで長時間覚醒していると、普段寝つきにくい人でもすぐに入眠し、深い眠りが出現することが知られています。いったん眠りに入ると睡眠欲求は急速に減少し、その人にとって十分な時間だけたっぷりと眠ると睡眠欲求は消失して私たちは覚醒します。
第二のメカニズムは、覚醒力(赤矢印)です。覚醒力は体内時計から発信されるシグナルの指示で、交感神経の活性化、覚醒作用のあるホルモンの分泌、深部体温(脳温)の上昇などによりもたらされます。覚醒力は日中を通じて増大し、徐々に強まる睡眠欲求に打ち勝ってヒトを目覚めさせます。眠りのメカニズムe−ヘルスネットより引用
睡眠欲求とは?
睡眠欲求は、疲労の蓄積とともに比例して増えていき、目覚めている時間が長くなるほど強くなります。
これは、身体の危険を知らせるために痛みが発生したり、エネルギー不足を知らせるために空腹を感じたりするのと同じように、「疲労を回復させる必要性」を知らせるためのサインとして睡眠欲求があると言われています。
そして、眠ることによってこの睡眠欲求は解消されていき、自然に目覚めることができるのです。
※睡眠の質が悪いと、寝ても疲労回復が不十分な場合もあります。
覚醒力とは?
覚醒力は、睡眠ホルモンと呼ばれる「メラトニン」により急速に低下していき、覚醒力が睡眠欲求を下回ることで急激に眠気を感じるようになるのです。
この覚醒力をコントロールしているのが「体内時計」であり、体内時計が狂うことで覚醒力が低下していきます。
つまり、日中に急激に眠気に襲われないようにするためには、体内時計を正常に保つ必要があるということです。
日中の 眠気 を防ぐポイント

さて、眠気が起こるメカニズムがわかってきたところで、日中の眠気対策のポイントを見ていくことにしましょう。
眠気 を防ぐ方法①:体内時計を整える
さて、前述した通り、日中に眠気が起こらないようにするためには「覚醒力」が正常に機能している必要があり、そのために重要なのが「体内時計」を正常に保つことです。 体内時計を正常に保つポイントは以下の3つ。
1、起床後、朝日をたっぷり浴びる
体内時計は太陽光を浴びることにより、活動時間であると身体が認識することでリセットされるので、日中活発に動けるようになるために覚醒力が増大していきます。
また、朝に太陽光を浴びることによって、睡眠の質を上げるのに欠かせない「メラトニン」の前駆体である「セロトニン」も分泌されるようになります。 つまり、朝にセロトニンが分泌されることによって、夜にメラトニンも生成されやすくなろので、睡眠の質を上げることもできます。
関連記事:睡眠ホルモン『メラトニン』の機能と効果【睡眠改善】
2、起床時間を統一させる
起床時間を統一させることによって、睡眠時間が制限されるため、自然に夜更かし対策にもなります。
また、1日のスタート時間を固定することによって、日中の覚醒力のピークの時間帯を固定できるので、日中のパフォーマンスのバラつきも防ぐこともできます。
どうしても寝たりないなと感じるのであれば、寝る時間をズラして、自分にあった就寝時間を見つけていくことが大切です。
3、日中はなるべく部屋を明るくし、寝る数時間前から徐々に部屋の明かりを暗くしていく
本来、人は日中明かりが出ているときに活動し、夜暗くなるころに休息をとる習慣を続けてきた生き物です。そのため明かりは、1日の活動時間を決める重要な手がかりになっています。
なので、日中はなるべく明るい環境で過ごし、夜は明かりを暗くしていくのが自然です。
また、昼光色には青空の光と同じ光の周波数が含まれていると言われているため体内時計が狂いやすくなるので、夜は昼光色の明かりは避け、暖色系の間接照明にするのがベストです。
眠気 を防ぐ方法②:覚醒力の低下を防ぐ
眠気は覚醒力が睡眠欲求よりも下回ることで起こると前述しましたが、当然ながら日中眠気に襲われないようにするためには覚醒力の低下を防ぎ、覚醒力を高めていく必要があります。
主に、覚醒力で重要なのが、覚醒ホルモンと呼ばれている「オレキシン」です。
「オレキシン」とは?
つまり、日中の覚醒を維持して眠気に襲われないようにするためには、オレキシンが正常に分泌されていることが大切です。
オレキシンは日中多く分泌されており、夜になると分泌量が減って覚醒力が落ちることによって眠気がおきます。
実際に、オレキシンの結合を阻害する睡眠薬が医療現場で使われているほどで、それだけ覚醒力の主力と言ってもいいほど覚醒力にはオレキシンの分泌が大切です。
また、日中に急激な睡魔に襲われて起きているのが困難になる睡眠障害である「ナルコレプシー」は、オレキシンの分泌がうまくいかないことが原因で起こります。
視床下部外側野に存在する神経細胞が産生しているオレキシンは、食欲や報酬系に関わるほか、睡眠や覚醒を制御することが知られている。オレキシンをつくる神経細胞が消滅すると、ナルコレプシーという睡眠障害になる。 Wikipedia「オレキシン」より引用
視床下部とは?
代表的なものでは、獲物をとる行動を促す摂食中枢や、食の限界を知らせる満腹中枢、喉の乾きを知らせる渇中枢、性行動を促す性中枢などがあります。 また、視床下部は、交感神経や副交感神経や内分泌機能の調節なども行っております。
内分泌機能で調節される内分泌とは、成長ホルモンや性ホルモン、甲状腺ホルモンなどです。
オレキシンを増やすには?
眠い状態で狩りや採集をするのと、頭がスッキリ目覚めた状態で狩りをするのとでは、どちらの方がより成功確率が高いか想像に難くないですね。 また、オレキシンが生成される場所と摂食中枢(空腹を知らせて摂食行動を促す機関)が同じ視床下部にあるため、摂食中枢が刺激されるとオレキシン生成も増えやすくなるというわけです。
さらには、血糖値が下がることによってもオレキシンが活性化すると言われています。 なので、何かしら集中したい作業前には、軽く食事や血糖値を上げる飲み物をとっておくと、作業中に血糖値が下がるタイミングでオレキシンも活性化していくのでおすすめです。
ただし、血糖値が乱れるとオレキシンの量も減るので、糖分のとりすぎには気をつけましょう。あくまで血糖値を「軽く」上げるのがポイントです。
よく食後は眠くなりやすいといいますが、これは血糖値の急激な増減によりオレキシンの量が減ったためと考えられます。 血糖値を上げ過ぎない食事では「低GI食品」がおすすめ。
〈おすすめ低GIの食品一覧〉
- バナナやリンゴ、イチゴなどの果物類
- ヨーグルトやチーズなどの乳製品
- アーモンドなどのナッツ類
- ハイカカオチョコレート(※甘いチョコレートは高GIの物が多い)
- サツマイモ
- ゆで卵
- サラダチキン
- 大豆製品
- きのこ類
- 海藻類
- 玄米、そば、ライ麦パン
- 寒天、こんにゃく、春雨
- 葉物野菜全般
そして、もう1つのポイントが「味覚刺激」です。
オレキシンは食べ物を味わっているとき、つまり「味覚」が刺激せれているときにも増えると言われています。 味覚が刺激されることで、前述した摂食中枢も刺激され、摂食中枢と同じ視床下部にあるオレキシン生成細胞も活性化されると言う仕組みです。
オレキシンを増やす方法をまとめると以下の通り。
↑これをみると、空腹になる度に自然に休憩をとれるようになるので、間食を挟みながら作業するのは理に叶っているかもしれない…笑
眠気 を防ぐ方法③:アデノシンを取り除く
睡眠欲求が高まるにつれてアデノシンが分泌されていき、脳内にある受容体であるアデノシンのレセプターに一定量アデノシンが溜まることで眠気が起こります。
言い換えれば、この受容体からアデノシンを取り除くことで一時的に眠気を防ぐことができるわけです。
アデノシンを取り除く方法では「カフェインナップ」がおすすめです。
カフェインナップとは?
カフェインの覚醒作用は、カフェインをとってから20〜30分前後に効き始めます。
なので、仮眠の直前にカフェインをとることにより仮眠が終わったタイミングでちょうどカフェインが効いてくるので、さらに覚醒力にブーストがかかるという仕組みです。
カフェインナップは、昼食後の覚醒力が落ちてきたタイミングで行うのがおすすめで、アデノシンを取り除くことで頭がスッキリした状態でまた午後からの作業に取り組むことができます。
眠気 を防ぐ方法④:身体を冷やす
眠気と深部体温には相関があり、深部体温が下がると眠気が強くなり、深部体温が上がると眠気が弱くなります。 これは、睡眠時に神経の働きを抑えて休ませるために脳の温度を下げる必要があるため、睡眠欲求が強くなった(疲労が蓄積した)タイミングで深部体温を下げるように身体が反応するためです。
つまり、深部体温が下がることによって身体が「眠る準備ができた?」と認識して眠気が起こるわけです。
「それなら深部体温を上げればいいの?」と思うかもしれませんが、むしろ逆です。 たしかに体温を上げると上がっている間は目が覚めます。ですが、身体が熱くなった体温を下げようと放熱するので、結果的に深部体温が下がっていき、徐々に眠気が強くなっていきます。 よく暖房がきいた部屋で眠くなるのはこのためです。
反対に、手足や首周りを冷やして体温を下げていくことで、今度は体温を上げようと血流を増やすので、眠気を弱くすることができます。
トピックス:「コーヒーの飲み過ぎ」が眠気の原因になる?
コーヒーの飲み過ぎは深部体温を下げるので注意が必要です。 過度なカフェインの摂取は血行不良を引き起こし、それが体温の低下につながると言われています。
また、カフェインの利尿作用により放熱されるので、それも深部体温が下がる原因になります。
その結果、深部体温が下がることで眠気が引き起こされていくというわけです。 「コーヒーをいっぱい飲んでるはずなのに眠い」となるのはこのためですね。
何事もほどほどに、が大切です。
眠気 を防ぐ方法⑤:鉄不足を防ぐ
「寝ても寝ても眠い」はひょっとしたら鉄分不足のせい? よく眠気が強いときにあくびが出ますが、これは脳の酸素が不足することによって起こる生理現象です。
不足した酸素を一度に大量に取り入れるために、あくびをすることで酸素を取り入れているわけです。 そして、血中の酸素を全身に送る役割りをしているのがヘモグロビンであり、ヘモグロビンは鉄分から作られています。
つまり、鉄分が不足することで酸素不足になりやすくなり、細胞や脳のエネルギー効率も落ちて眠気が取れにくくなるわけです。
日中、頭が回らない、眠気が取れない、疲れやすいという方は一度、鉄分不足による酸素不足を疑ってみて下さい。
〈鉄分が不足すると…〉
鉄分不足…恐ろしや。 Kuはよく「鉄分グミ」を食べております。手軽に美味しく鉄分補給できるのでおすすめb
〈鉄分不足の原因〉
- お茶やコーヒーの飲み過ぎ→渋み成分でありカテキンの一種である「タンニン」が鉄分の吸収を阻害する。
- ミネラル不足の偏った食事
- 月経や怪我、胃腸ガンや痔などによる出血
〈鉄分をとるには?〉
鉄分は、赤身肉、赤身魚、レバー、貝類、プレーンなどに多く含まれています。 野菜などにも鉄分が含まれている物がありますが、野菜の鉄分は「非ヘム鉄」で吸収効率が悪いので、鉄分は「ヘム鉄」を含む赤身肉や貝類からとるのがおすすめ。
また、ビタミンCやクエン酸と一緒にとると鉄分の吸収効率が上がるのでおすすめです。ぽん酢やレモン汁を使った味付けなどがよいのではないでしょうか。
ビタミンCを多く含む食品は、アセロラ、ケール(青汁)、パセリ、パプリカ、キウイフルーツ、芽キャベツ、焼海苔、おろしショウガ、ブロッコリーなどがあります。
Quの個人的な好みではありますが、パプリカとアサリのボンゴレパスタなんかビタミンCと鉄分が同時にとれて、美味しいのでおすすめです(笑)
眠気 を防ぐ方法⑥:交感神経を刺激する
〈交感神経とは?〉
交感神経は自律神経の一種で、血圧を高めたり、血流を増やしたり、心拍数を増やしたりすることによって、身体を「活動モード」にさせる神経のこと。 つまり、交感神経をうまく刺激することによって、日中活動的に動けるようになります。 〈交感神経を刺激する方法〉
眠気 を防ぐ方法 まとめ
- 眠気に関わるシステムには、「睡眠欲求」と「覚醒力」がある
- 覚醒力が落ち、睡眠欲求の方が覚醒力より大きくなることによって眠気が引き起こされる
- 日中眠気に襲われないようにするためには、覚醒力を下げないことが大切
- 睡眠欲求と覚醒力のバランスを司っているのが「体内時計」
- 覚醒力を下げないためには体内時計を正常に保つことが大切
- 体内時計は、朝日をたっぷり浴びることでリセットされる、また、起床時間や食事の時間などの生活リズムをなるべく統一することも大切
- 覚醒力を支えている物質には、脳の覚醒ホルモン「オレキシン」がある
- オレキシンは、「食への期待(摂食中枢の刺激)」と「味覚刺激」によって増やすことができる
- 血糖値が緩やかに下がることでオレキシンが活性化する
- 作業前の間食には血糖値を緩やかに上げる「低GI食品」がおすすめ
- 睡眠物質である「アデノシン」が一定量溜まることで、脳は眠気のサインを出す
- アデノシンを取り除くことで、一時的に眠気を覚ますことができる、ただし、根本的な疲労が回復したわけではないので注意
- カフェインはアデノシン受容体と結びつくことなできるので、アデノシンが溜まりにくくなる。
- 仮眠によって、アデノシンを取り除くことができる
- 仮眠前にカフェインをとる「カフェインナップ」をすることで、仮眠後にカフェインの覚醒作用が働く(カフェインの覚醒作用はカフェインをとってから約20〜30分かかる)ので、仮眠後にすぐに活動しやすくなる
- 深部体温が下がることによって眠気が引き起こされる→日中は深部体温を高めておくことが大切
- 過度のカフェインは血行不良を引き起こし、深部体温を下げる原因になるので気をつける
- 運動や血行をよくするストレッチやマッサージ、身体を温める生姜や温かい飲み物(特に白湯がおすすめ)などで深部体温を高めることができる
- 「寝ても寝ても眠い」は鉄分不足による、脳の酸素濃度の低下が原因の場合がある
- お茶やコーヒーに含まれている「タンニン」が鉄分の吸収を阻害するので、鉄分不足の原因になる
- 鉄分は吸収率の悪い「非ヘム鉄」である野菜類よりも、吸収率のよい「ヘム鉄」である赤身肉や赤身魚、貝類からとるのがおすすめ
- 鉄分はビタミンCやクエン酸と一緒にとると吸収効率がよくなる
- 交感神経を刺激することにより血圧や血流が増えることで、身体を「活動モード」にすることができる
- 交感神経は、運動や、表情筋を使うことで刺激される
- また、温冷刺激によっても交感神経が刺激される→熱めのシャワーや冷水で顔や手足、首周りを冷やすなど
- 交感神経を刺激するアロマでは、レモングラスやローズマリーがおすすめ
「活力を高める方法」では、こちらの記事もおすすめです。
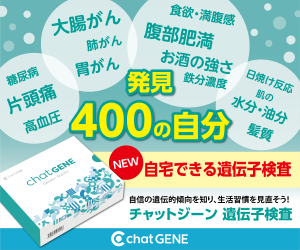
【気軽にコメントをどうぞ!】