【 世界 の 心理学 】「 ○○ 理論 」一覧
どうも、Kuです! 今回は世に広まっている心理学に関する様々な「 理論 」を紹介していきます。
心理学の研究は自然科学や哲学、天文学などの分野に比べると、約150年とまだまだ日が浅い学問ではあります。
しかし、近代において心理学は商業や医療、人間工学や犯罪の抑止、道路標識に至るまで実に多岐にわたる分野に応用されており、人間の豊かで快適な生活を送るためには欠かせないものになっています。
心理学は本当に奥が深くておもしろいですね!
人生の質を高めていくためにも心理学を上手に応用してみてください!
ヒグビーの理論
いわば「記憶の仕組みを応用した記憶のコツ」を体系化した理論。
どちらかというと「心理学」というよりは「認知科学」よりの理論です。
アメリカの心理学者「ケネス・ヒグビー」によって提唱され、7つの記憶に関する仕組みにまとめられています。
- 「有意味化」 意味を理解することで記憶に残りやすくなる
- 「組織化」 ばらばらの情報よりも、なんらかの法則性のあるまとまった情報の方が記憶に残りやすい
- 「連想」 新しい情報をもうすでに知っている情報に結びつけることで記憶に残りやすくなる
- 「視覚化」 言葉や記号よりも図解などのイメージの方が記憶に残りやすい
- 「注意」 広い範囲を多面的に覚えるより、狭い範囲を集中して覚えた方が記憶に残りやすい
- 「興味」 好きな物や好奇心を刺激する事柄ほど記憶に残りやすい
- 「フィードバック」振り返えられた(反復された)情報ほど記憶に残りやすい
社会的交換 理論
実際に人間社会は、資源、情報、サービス、労働力、報酬、罰など、なんらかの「交換」によって成り立っているといえます。
そのなかでも人類最大の発明といわれている「お金」という概念がこの理論を表す最たるものです。
ちなみに、「費用対効果」という言葉がよく使われておりますが、「交換によって与えたものと受け取ったものの価値の差による損得計算」とも言えます。
心理学においては、「好意の返報性」がこの理論に当てはまるのではないでしょうか。
ちなみに「好意の返報性」とは、相手から好意や称賛などのなんらかの「報酬」を受け取ったら、それと同等もしくはそれ以上の報酬を相手に返したくなる心理が働くことをいいます。
クレッチマーの体系別類型論
もともとは、特定の精神疾患と体格の間に相関関係があるという仮定のもと研究された理論です。
これは「循環気質」「分裂気質」「粘着気質」の3つのタイプに分類されています。
また、体系と性格の関連を臨床した似たような理論で「シェルドンの類型論」というものもあります。
ちなみに体格説は多くの大衆にウケ、広がりましたが、統計学的な観点で疑問点が多く、現在はほとんどのパーソナリティ研究では使われておりません。
《循環気質の人の特徴》
- 体型:肥満型
- 関連する精神疾患:躁うつ病
■循環気質の性格・気質の傾向
- 社交的で親切
- 陽気でおしゃべり
- 環境適応力が高い
- 開放的
- 快活な気分と憂鬱な気分を繰り返す
《分裂気質の人の特徴》》
- 体型:細身型
- 関連する精神疾患:統合失調症(精神分裂病)
■分裂気質の性格・気質の傾向
- 非社交的
- 口数が少ない
- 自閉的
- 上品で繊細
- 孤独な理想家
- 冷淡な支配者
- 利己的
《粘着気質の人の特徴》
- 体型:闘士型(筋骨型)肩幅が広く骨格が頑丈
- 関連する精神疾患:癲癇(てんかん)
■粘着気質の性格・気質の傾向
- 秩序を重んじる
- 粘り強い
- 頑固
- 執着心が強い
- 激情家
- 几帳面
- 興奮しやすい
シュプランガーの価値類型論
1.『理論型』: 「理論が通じること」に価値を置く
客観的な情報を重視し理屈に合わないことはしたくない。感覚のみで物事を判断することはほとんどなく、判断材料には知識や情報を重視する
2.『経済型』 :「金銭や社会的地位」に価値を置く
結果を重視し基本的に損得勘定で動く。利己主義的な選択をとりがち。
3.『審美型』 :「美しい物や楽しいもの」に価値を置く
芸術的な活動に惹かれ、最終的には五感を頼りに直感的に物事を判断することが多い。
4.『宗教型』 :「信仰心や道徳的な行い」を重視する
魂のあり方など、神秘的なものやスピリチュアルな事柄に惹かれやすい。
5.『権力型』 :「人の上に立ち、自らの力で他人をコントロールすること」に喜びや満足感を求める。
上下関係を重視し、勝ち負けにこだわる。競争心や上昇志向が強い。
6.『社会型』 :「社会への貢献」に価値を置く
他者を助け支え、他者の役に立てることに喜びを感じやすい。
協調性に優れており、人とのつながりを重視する。
ユングの性格類型論
「世界でもっとも有名な性格タイプ論」ともいわれています。
ユングは人の性格を、人間が持つ「思考」「感情」「感覚」「直感」の4つの心理機能の強さの傾向と心的エネルギーの向かう方向性「外向性」と「内向性」の2つの心的態度を組み合わせた8つのタイプに分類しました。
- 「思考(区別原理)」タイプ
→何事も論理的にとらえ、様々な現象を比較・分析して原因と結果の因果関係を明らかにしながら物事を判断するタイプ、「メリット・デメリット」に敏感。医者や弁護士、学者などに多い。 - 「感情(関係原理)」タイプ
→理屈よりも感情や気持ちを優先するタイプ、「好き・嫌い」で物事を考えがち。芸能人などのエンターテイナーに多い。 - 「感覚(現実性)」タイプ
→物事を「快・不快」でとらえるタイプ、観察力に優れており、五感の情報を頼りに状況を理解しようとする。アーティストに多い。 - 「直感(可能性)」タイプ
→イメージやひらめきを優先するタイプ、「かもしれない」という仮説を次々に立て、思いついたアイデアを形にすることを好む。研究者やクリエイターに多い。
- 「外向性」:物事の関心を「周囲の環境」に向けるタイプ
→人間同士の営みを楽しみ、人々と共に過ごすことで活力を得ることができる - 「内向性」:物事の関心を「自分自身の精神状態」に向けるタイプ
→大勢でいるよりは、独りでいることを好む
また、上記の機能はいづれもあくまでも「傾向」であり、どれがどの程度強く機能しやすいかには個人差があります。
つまり「思考」と「直感」が同等程度に強く機能しやすい人もいれば、4つの機能がバランスよく機能する人もいるということです。
例1、「内向型思考直感タイプ」思考4、感情1、感覚、2、直感3
例2、「外向型感情感覚タイプ」思考1、感情5、感覚3、直感1
例3、「外向型バランスタイプ」思考3、感情3、感覚2、直感2
例4、「内向型直感特化タイプ」思考1、感情1、感覚1、直感7
ただ、「思考」と「感情」、「感覚」と「直感」は相反すると言われており、どちらかの傾向が強くなると相反するもう片方の機能は弱くなると言われています。
ビッグファイブ 理論
人格は「外向性」「開放性」「勤勉性」「協調性」「神経症傾向」の5つの要素から構成されていると言われています。
- 「外向性(社交性)」
外界へのかかわり方や、新しい活動への意欲の高さを表す - 「開放性」
新しい分野や世界に対する好奇心や芸術的感受性の強さを表す、「変化と安定」のどちらを求めるかがわかる - 「誠実性(勤勉性)」
自制心や責任感、物事の継続力の強さを表す、「衝動に対する自己コントロールの高さ」ともいえる - 「協調性」
他者への共感力や思いやりの強さを表す、周囲との関わり方の傾向がわかる - 「神経症傾向(メンタル耐性)」
不安やストレス、ネガティブな出来事に対する反応の強さを表す、外界の刺激をダイレクトに受けやすいかどうかがわかる
現在ではこの「ビッグファイブ」を応用、発展させた研究も多数存在し、その中でも「コスタ&マークレー」の提唱したモデルが最も有力とされています。
人の性格や気質を解明する「パーソナリティ研究」には様々な歴史があり、「心理学」の研究は約150年以上をかけて世界中の多くの研究機関や心理学者によって行われてきました。
しかし、それぞれの研究は独立して行われており、それぞれの研究の関連性がとぼしく見解がバラバラでした。
その中でも、類似の結果をまとめ上げ性格を構成する要素を5つの因子に統一したのが「ビッグファイブ」と言われています。
つまり、「ビッグファイブ理論」は長年にわたる「パーソナリティ研究の集大成」とも言える理論でもあるわけです。
現在では「最も信憑性の高い性格診断法」として確立しています。
スリーセット 理論
- 1回目:「この人はこういう人かもしれない」という印象が残る
- 2回目:「あ、やっぱりこの人は○○な人だ」もしくは「あれ、○○だと思っていたけど実は意外と~なところもある人なんだ」という初対面の印象の再確認を行う
- 3回目:「この人は○○な人だ」という印象が固定化される
- 4回目:3回目で抱いたイメージとほとんど変わらず
「スリーセット理論」はよく「初頭(プライマシー)効果」と組み合わせて用いられることが多いです。
「初頭効果」とは、「最初に与えられた情報ほど印象に残りやすくその後の判断材料として強く影響されやすい」という心理効果のこと。
たとえば、まるっきり同じ内容を伝えられたとしても、長所からから紹介されたときと短所から紹介されたときとではまるっきりその人の印象が変わります。
- 長所が先:優しい、知的、誠実、批判的、怒りっぽい
- 短所が先:怒りっぽい、批判的、誠実、知的、優しい
「初頭効果」を実証した実験では「ソロモンアッシュの実験」が有名です。
出会ってから3回目まではなるべくネガティブな印象を排して好印象を残せるようにするのがベターです。
イノベーター 理論
イノベーションとは、「人々の生活を豊かにする新しいアイデアを基にしたサービスや商品、考え方」のこと。
アメリカのスタンフォード大学の社会学の教授である「エベレット・M・ロジャース」によって1962年に提唱されました。
消費者のタイプを5つに分類して、どのように市場へ普及されていくかを分析しまとめられています。
- イノベーター(革新者):「目新しさ」を求めて積極的に採用する人々、市場全体の2.5%を占める
YouTuberで例えるなら、日本にYouTuberの文化を広めるきっかけを作ったヒカキンさんやはじめしゃちょ―がこれに該当します。 - アーリーアダプター(初期採用者):流行に敏感で情報収取を積極的に行う人々、市場全体の13.5%を占める
また、情報発信も積極的に行い市場拡大への影響力も非常に大きいのも特徴のひとつ。
アーリーアダプターは流行を広める役割も担うことから「インフルエンサー」もしくは「オピニオンリーダー」と呼ばれることもあります。
YouTuberで例えるなら、次々と新しい事業を仕掛け株価をも動かす天才児ヒカルさんが該当するのではないでしょうか。 - アーリーマジョリティ(前期追随者):新しい商品やサービスに対して比較的慎重であるが平均よりは早くに新しい物を手に入れる、市場全体の34.0%を占める アーリーアダプターから広まった流行を応用してさらに市場全体に浸透させる橋渡しとなることから「ブリッジピープル」と呼ばれることもあります。
- レイトマジョリティ(後期追随者):新しい物事に対して比較的懐疑的な人々、市場全体の34.0%を占める 過半数の人々に受け入れられて初めてその商品を試そうとするところから「フォロワーズ」と呼ばれることもあります。
YouTuberで例えると、YouTubeの全盛期から少し遅れて、安定しだした時期から参入した宮迫氏やカジサック氏をはじめとする芸能人の参入がこれにあたります。 - ラガード(遅滞者):最も保守的な人々、市場全体の16.0%を占める 流行への関心がほとんどなく、イノベーションよりも昔ながらの伝統を重視する人々とも言えます。
認知的斉合性 理論
人間の身体には「恒常性(ホメオスタシス)」という機能が備わっています。
これは、なんらかの作用により体内環境が不均衡(不安定)な状態になった場合、均衡状態に戻してバランスを整えるための機能が自動的に働く機能のことです。
この、生命活動を維持するために体内環境のバランスを一定に保つ働きをすることを「恒常性」といいます。
たとえば、体温を下げるために汗をかいたり、血糖値を下げるためにインスリンを分泌させたりする働きが恒常性に該当します。
さらに恒常性は、人の精神活動、認知活動においても働きます。
心理学においては、人は精神活動や思考における矛盾や不安定さを解消するために、新しい解釈を加えたり認知内容を変化させたりしながら辻妻を合わせる作業を無意識のうちに行っているそうです。
これが「認知的斉合性」です。
またこの心理作用は、自分の思考や精神状態、態度や行動に一貫性をもたせることでバランスをとる働きをすることから、別名「一貫性の原理」とも呼ばれています。
「認知的斉合性理論」はさらに、後述する「認知的均衡理論(バランス理論)」と「認知的不協和理論」などに分けられます。
認知的均衡 理論 (バランス理論)
別名「P-O-X理論」とも呼ばれており、特定の人物(P)・第三者(O)・物事(X)の3つの要素の関係性のバランスをとろうとする心理が働きます。
- 「好き」などの好意的な関係性なら「+」
- 「嫌い」などの否定的な関係性なら「-」
として判断します。
三つの全ての関係が「+」になるか、いずれか二つの関係が「-」になる場合に「均衡状態」といえます。
そして、いずれか一つが「-」である場合、「不均衡」の状態であると言え「P-O-X」のうちいずれかの要素を変容させることでバランスをとろうとします。
たとえば、
- P:自分
- O:恋人
- X:海
- 「自分」は「恋人」が好き=「+」
- 「自分」は「海」が「嫌い」=「-」
- 「恋人」は「海」が「好き」=「+」
「-」がひとつ=「不均衡」→バランスを保ちたい!
→「恋人」を「嫌い(-)」になるか「海」を「好き(+)」になるか「恋人」を「海嫌い(-)」してバランスをとろうとします。
認知的不協和 理論
つまり、「行動の正当性を保つために心理状態を変化させること」を「認知的不協和理論」といいます。
たとえば、
- 世話をしているうちにいつの間にか相手を好きになる
- 禁煙の苦痛を避けるために喫煙の正当性を探しだす
- 理由もなく頻繁に謝る人に対して怒りの感情が湧く
- 笑顔を作っているうちに本当に楽しくなる
など。
「認知的不協和理論」を実証した研究では「レオン・フェスティンガーとメリル・カールスミスの実験」が有名。
社会的比較 理論
人は自己評価を正確に把握するために他者との比較を無意識のうちに行っています。
これは「自分の社会における立ち位置」を確認したいという欲求があり、他者と比較することで満足感を得ようとする心理が働くためです。
また、比較対象を選ぶ際はメンタルの状態によって左右されます。
- 自信が高まっている場合「上方比較」→自分より優れた人と比較する
- 自信が低下している場合「下方比較」→自分より劣っている人と比較する
たとえば、落ち込んで自己評価が低いときに、自分より不幸な境遇にいる人を見ることで安心感を得る人がいますが、その心理はこの理論によって説明がつきます。
意思決定 理論
ゲーム理論とは、ビジネスや人間社会における人物をプレイヤー(ゲーム参加者)とみなし、互いに与える影響を考慮しながら意思決定を行う理論です。ビジネスシーンにおいては、自らの行動によってどのような利益が生まれるのか、どのようにリスクを抑えられるのかなどを検討して行動に移します。
ハーズバーグの2要因 理論
従業員の仕事に対する満足度に関わる要因は、主に「動機付け要因」と「衛生要因」の2種類に分けられます。
- 動機付け要因(モチベーター):仕事の「満足感」に関わる要因 「達成」「承認」「責任」「やりがい」「昇進」「昇給」など、社会的な「欲求」を満たすための条件が多い。
- 衛生要因(ハイジーンファクター):仕事の「不満感」に関わる要因
「上司や同僚との人間関係」「給与」「福利厚生」「経営方針」「作業条件」など、職場環境に関する条件が多い。
「満足」と「不満」の要因ははっきり分かれており、仕事へのモチベーションを高めるためには両方が解消されている必要があります。
つまり、不満を取り除いただけでモチベーションが上がるわけではなく、また、満足感だけ高めても不満要因が解消されなければモチベーションは下がる可能性もあるというわけです。
成功恐怖 理論
目標を達成し「成功した際に陥るであろうリスク」を無意識に想像することによって不安感情が強くなります。
人はこの成功のリスクからくる不安感から逃れるために、成功するための行動を避ける選択をしてしまいやすいそうです。
たとえば、以下のような想像をしやすいです。
- 成功して注目されることで非難される頻度も多くなる
- 時間に縛られ自由な時間が減る
- 成功は一瞬で、途中で転落するかもしれない
- やりたくないことまでする必要がある
- 常に周囲からの期待やプレッシャーがつきまとう
- 時間と労力がすべて無駄になる恐れもある
要するに、「成功恐怖」は過度な不安からくるものなので、不安対策をすることで解消できます。
「不安」への対策を知りたい方は、よろしければ以下の記事をご覧ください。
>>【メンタル強化】 不安 を減らす思考法と おすすめ習慣
吊り橋 理論
ある出来事が起こった際に、まず認知(つまり解釈)が起こるのか、それとも感情が先に生まれるのかを実証しようとした理論のこと。
- 「出来事→出来事への認識・精神作用→感情」
- もしくは、「出来事→感情→出来事への認識・精神作用」
出来事に対して感情が発生する際の経路を調べる実験に、「吊り橋」を使ったことが名前の由来になっています。
「吊り橋理論」を応用した有名な実験に「恋の吊り橋効果実験」があります。
実験は、18歳から35歳までの独身男性を集め、バンクーバーにある高さ70メートルの吊り橋と、揺れない橋の2か所で行われた。男性にはそれぞれ橋を渡ってもらい、橋の中央で同じ若い女性が突然アンケートを求め話しかけた。
その際「結果などに関心があるなら後日電話を下さい」と電話番号を教えるという事を行った。結果、吊り橋の方の男性18人中9人が電話をかけてきたのに対し、揺れない橋の実験では16人中2人しか電話をかけてこなかった。
実験により、揺れる橋を渡ることで生じた緊張感がその女性への恋愛感情と誤認され、結果として電話がかかってきやすくなったと推論された メリーランド大学のグレゴリー・ホワイトは、吊り橋の緊張感を恋愛感情と誤認するには、実験で声をかける女性が美人かどうかで結果が左右されるのではと考えた。
実際にメイクで魅力を低下させた女性で同様の実験を行ったところ、美人ではない場合には吊り橋効果は逆効果であることがわかった
Wikipedia「吊り橋理論」より引用
これは「恋愛心理学」において最も有名な心理効果といってもいいのではないでしょうか。
簡単に言うと、吊り橋を渡ったときの緊張や興奮を、相手の魅力に対する緊張や興奮だと誤認することによってその相手に魅力を感じてしまう効果のことを言います。
しかし、上記にもある通りこの効果は、「もともと魅力的だと感じる相手」のみに限定されますので要注意です。
色彩論
ニュートンは色彩を「光の屈折率による波長の違い」ととらえ、ただただ数学的に解釈されています。
それに対し、ゲーテの色彩理論はどちらかというと、「人の感覚や心理の影響による色彩の見え方の違い」をも実証しており「色彩心理学」の先駆けにもなっています。
さて、いかがだったでしょうか。
本当はまだまだ心理学の原理や法則などありますが、それはまた次の機会に^^
それでは!
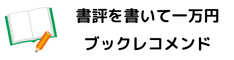
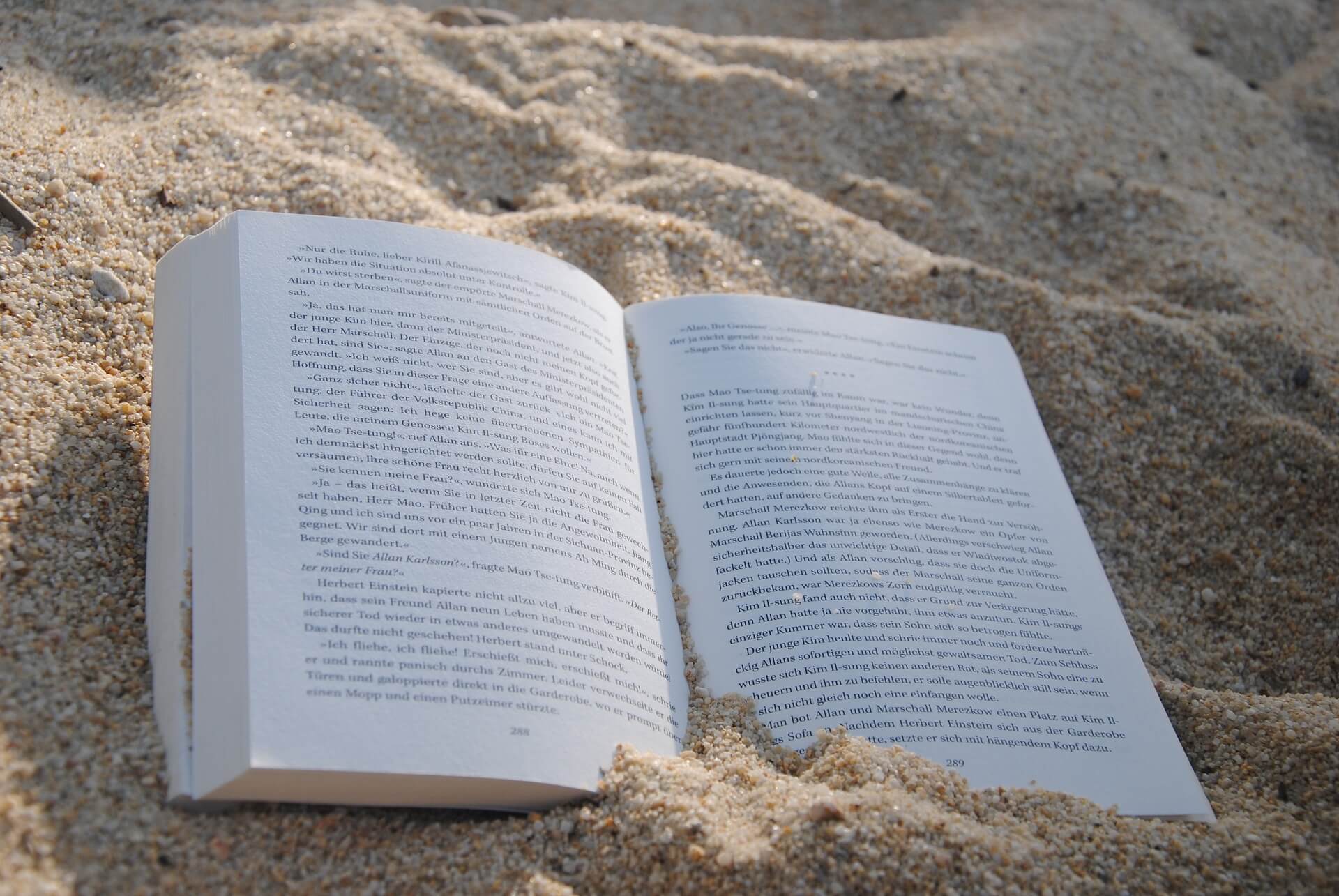

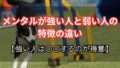

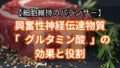
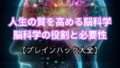



コメント