【 世界 の 心理学 ②】 これは使える?「 ○○ 仮説 」一覧
どうも! Kuです。今回は前回に引き続き「世界の心理学」そのなかでも「 心理 仮説 」を紹介していきます。
《仮説の意味》
か‐せつ【仮説】ある現象を合理的に説明するため、仮に立てる説。実験・観察などによる検証を通じて、事実と合致すれば定説となる。Weblio辞書より引用
まぁつまり、なんらかの理由により証明には至っていないけれど、「特定の心理現象を説明するには都合のいい合理的な解釈」といえます。
今回解説する心理学
- 恋人選びの心理仮説
- 怒りを回避するための心理仮説
- 幸福度に関わる心理仮説
- 表情と感情に関する心理仮説
- モチベーションに関する心理仮説
〈関連書籍〉
マッチング 仮説
別称「つり合い仮説」と呼ばれている通り、人は「自分と釣り合いの取れていると感じる相手を無意識のうちに恋人に選ぶ」という仮説のこと。
「つり合っている」とは、外見だけではなく内面まで含めた総合的な魅力度で測っているそうです。
- 容姿(雰囲気や表情、仕草なども含む)
- 地位、経済力
- 知性、能力、精神力
よく「似たもの夫婦」という言葉を耳にしますが、この仮説による心理が働いているいい例です。
また、「ものすごく美人で性格もいいのに独身で恋人もいない」という人もわりとよく聞きますが、誰ともつり合いが取れず無意識に選択肢から外されていることが多いということかもしれません。
自責の念による反応増幅 仮説
人は、相手に対して自責の念を感じてしまうと、その自責の念による嫌悪感(つまり自分自身への嫌悪感)を増幅させ、自責の念を感じさせる原因になった相手への嫌悪感に転換させる心理が働きます。
たとえば、
《相手をしかった場合》
- 相手をしかる
- →相手が傷つき落ち込んでいる様子を見せる
- →それを見て、相手を傷つけてしまった罪悪感が芽生える
- →自責の念(自分に対する嫌悪感)を抱く
- →「なぜ、相手が悪いのに自分がこんな不快な気持ちにならなければならないのか?」という思考がわき起こる
- →自分への嫌悪感を解消するために相手への嫌悪感に転換する
- →もともとあった相手への嫌悪感+自責の念から転換された嫌悪感
- →相手への嫌悪感が増幅された形で残る
- →相手に対してもっと攻撃的になる
なので、まぁ間違いを指摘されたら、まずは落ち込まずに素直に反省して前向きな姿勢を見せた方が良いということです。
「自分は被害者」みたいなそぶりを見せる悲劇のヒロインって観てて不愉快になる人もいますからね。
気をつけましょう!
ボトムアップ説/トップダウン説
「幸福とは何で決まるのか?」を考えた仮説のこと。
《ボトムアップ説》
「プラスとマイナスの出来事の総数が幸・不幸を決める」という考え方。 この考え方では、不幸な出来事が少なく、かつ、幸福な出来事が多ければ多いほど幸せだと考えます。
《トップダウン説》
「出来事ではなく個人の捉え方や感じ方が幸福感を決める」という考え方。
同じ出来事であっても、「幸福」だととらえる人もいれば「不幸」だととらえる人もいるわけであって、結局は「幸福かどうかを決めるのはその人の考え方次第」と考えます。
人によって幸福への解釈が異なり、どちらも完全に否定できないことから、どちらの仮説も実証は難しいとされています。
ただ、現在では一般的で客観的なデータで調査ができるため「ボトムアップ説」の方が有力だそうです。
つまり、
- 客観的な事実をもとにした幸福度:ボトムダウン説
- 主観的な観点から考察された幸福度:トップダウン説
といえそうです。
ちなみに、筆者は「トップダウン説」派です(笑)
表情フィードバック 仮説
「表情フィードバック仮説」とは簡単に言うと、「表情を作ることで感情が引き起こされる」という仮説。
つまり、「嬉しいから笑う」のではなく「笑うから嬉しい」という考え方です。
もともとは1880年代にアメリカの心理学者「ウィリアム・ジェームズ」とデンマークの心理学者「カール・ランゲ」が別々に立てた仮説がもとになった「ジェームズランゲ説」が発端です。
これは「外からの刺激に対して身体的変化(表情)が先か、情動(感情)が先か?」を検証しようとした仮説のことです。
つまり、簡単に説明すると以下のようになります。
- 「ペットが亡くなる(刺激)→泣く(身体的変化)→悲しい(情動)」なのか
- 「ペットが亡くなる(刺激)→悲しい(情動)→泣く(身体的変化)」なのか
トロント大学のサスキンド博士(心理学)らの研究グループが、『ネイチャー神経科学』誌の2008年7月号に報告した実験 被験者に「恐怖」の表情と「嫌悪」の表情をさせると「恐怖」の表情を作ると「視野が広がる」「眼球の動きが速まる」「鼻腔が広がる」「呼気の気速が速くなる」といった身体の変化が起こり、「嫌悪」の表情をさせると「視野が狭くなる」「鼻腔が狭まる」「知覚が低下する」といった身体の変化が記録された Wikipedia「表情フィードバック仮説」より引用
目標の欲求勾配 仮説
「目標の欲求勾配仮説」とは「目標達成に近づけば近づくほど、モチベーションが上昇する心理現象」のこと。
《目標の欲求勾配の例》
- あと少しでタスクが完了する
- あと数ページで読破できる
- あと数時間したら就業時間
- あと数メートルで完走できる
など。
「中間ゴール」を設定したり、「目標の進捗状況」をすぐに確認できるようにしておくと目標の達成率が高まると言われていますが、この心理現象が働いているおかげです。
心理学 仮説 まとめ
- マッチング 仮説:自分と釣り合っていると感じる相手を無意識のうちに恋人に選ぶ心理仮説のこと
- 自責の念による反応増幅 仮説:傷ついたそぶりを見せて相手に自責の念を感じさせると、かえってその相手の怒りを増幅させてしまう心理が働くこと
- ボトムアップ説/トップダウン説:
幸・不幸の出来事の総数が幸福度を決める「ボトムアップ説」
出来事に対する個人の感じ方や考え方によって幸福度が決まる「トップダウン説」 - 表情フィードバック 仮説:表情をつくることで感情が生み出されるという仮説、つまり「笑うから嬉しくなる」ということ
- 目標の欲求勾配 仮説:ゴールが近づいていると認識することでモチベーションが一気に高まる心理現象が起こること、「中間目標」や「進捗チェックリスト」の効果はこの現象に由来する
〈関連書籍〉
「心理テクニック」に関しては、以下の記事もおすすめです。
>>【ビジネス】「買わせるテクニック」買い物の 心理学 5選
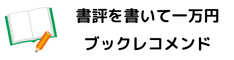



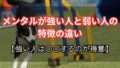

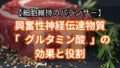



コメント