【心理学】 バイアス を引き起こす 心理効果 と 対策
どうも! Kuです。今回も前回に引き続き「 認知 バイアス 」について解説していきます。
認知バイアスとは、認知のゆがみの結果に起こる偏った価値観やものの見方をすることです。
「認知」とは、外界の刺激(五感)や観測できる状況に対して脳が何らかの判断や解釈をすることをいいます。そして、その「認知」をもとに思考することが「認識」です。
「刺激」→「認知」→「認識」
つまり、外界の世界から受け取った情報が思い込みや偏見によってゆがんだ状態で認知され、その間違った解釈によって認識される思考の偏りが認知バイアスです。
さて、ここでは、バイアスがかかる「心理効果」についても見ていきましょう。
いずれも実験による確証が得ているものばかりで、人間心理の面白さに気づけることでしょう。
バイアス を引き起こす 心理効果 一覧
- アンカリング効果
- 計画錯誤
- コンコルド効果
- ゼロサム思考
- ダニングクルーガー効果
- 透明性の錯覚
- ハロー効果
- バーナム効果
- フォールコンセンサス効果
- 気分一致効果
- 自己成就予言効果
- スポットライト効果
- プラシーボ効果
- サンクコスト効果
- 保有効果
- 寛大効果
アンカリング効果
「アンカリング効果」とは、「先に与えられた数字や予備知識などの情報によってその後の行動や判断に影響が与えられる」心理現象のこと。バイアスの一種。
《アンカリング効果の例》
- バーゲンセールの表示価格「定価9000円→今なら7500円!」
- 20%の確率で失敗する:80%の確率で成功する
- 3000円の商品だけ展示する→1万円の商品と3000円の商品(二つは同じ種類の商品)を並べて展示する
参考記事:アンカリング効果
計画錯誤
ノーベル賞経済学賞受賞の認知心理学者ダニエル・カーネマンは、楽観バイアスがかかる現象を「計画錯誤」という言葉で表現しています。 計画錯誤とは、「時間や予算など計画完遂に必要な資源を常に過小評価し、遂行の容易さを過大評価する傾向」で、人間の思考の非合理性ゆえに生じてしまう予測エラーのことです。
「富裕層になれない人の9割は、「楽観バイアス」人生」より引用
↓記事の後半で解説しております。
コンコルド効果
「埋没費用効果 (sunk cost effect)」の別名であり、ある対象への金銭的・精神的・時間的投資をしつづけることが損失につながるとわかっているにもかかわらず、それまでの投資を惜しみ、投資がやめられない状態を指す。超音速旅客機コンコルドの商業的失敗を由来とする。
Wikipedia「コンコルド効果」より引用
《コンコルド効果の例》
- 効果があまり見られないけど、使い続けていればいつかは効果がはずだ出てくるはずだ
- ハズレまくっているけど、買い続けていればいずれは宝くじが当たるはずだ
- 試験に落ちまくっているけど、勉強を続けていればいずれは合格できるはずだ
など。
ゼロサム思考
ゼロサムゲームというものがあります。 全員の得点の合計が常にゼロという方式のゲームです。全員の合計が0なので、誰かが点を取れば、他の人が点を失います。 これを日常に当てはめたものがゼロサム思考です。 幸せや喜びは限られている、なので誰かが幸せになれば他の人は幸せになれないという、まるで椅子取りゲームのような考え方でもあります。 ゼロサム思考では ・誰かの幸せのために自分が不幸にならなければいけない ・誰かが得をすると、自分は損をする ・誰かが褒められれば、自分は褒められない といった発想になります。
「ゼロサム思考とは?不幸しか生まない世界観」より引用
《ゼロサム思考の例》
- 誰かが得をすることで他の誰かが損をする
- 誰かが勝つことで他の誰かが負ける
- 誰かが評価されることで他の誰かは評価されなくなる
ダニングクルーガー効果
「ダニングクルーガー効果」とは、「能力が低い人ほど自分の能力を過大評価してしまう」という仮説に元ついた認知バイアスの一種。
《ダニングクルーガー効果の例》
- TVのクイズ番組出たらそこそこいい成績をとれそう
- まったくやったことないけどある程度はできそう
- 美人じゃないけど顔のレベルはクラスの中では中の上だと思う
参考記事:ダニングクルーガー効果
透明性の錯覚
透明性の錯覚とは自分のことは相手にちゃんと伝わっているだろう、という思い込みのこと。
「【対策必須】透明性の錯覚とは?74%の人から誤解される原因」より引用
↓記事の後半で解説しております。
ハロー効果
「ハロー効果」とは、「ある特定の目立つ特徴に、その他の特徴に対する評価が引っ張られる」心理効果のこと。バイアスの一種。
《ハロー効果の例》
- 見た目がいい人は優秀に見える
- 学歴や肩書で人格まで評価する
- 有名人と知り合いというだけで魅力的に見える
参考記事:ハロー効果
バーナム 効果
「バーナム効果」とは、「誰にでも当てはまる性格に関する曖昧な性質を、自分だけが当てはまる性格だととらえてしまう心理現象」のこと。
《バーナム効果の例》
- 血液型占い
- 心理テスト
- 占い師との会話
参考記事:バーナム効果
フォールコンセンサス 効果
「フォールコンセンサス効果」とは、「自分、もしくは自分が属する集団の考えや行動は常に多数派であり正常である」と思い込むことです。
「実在しない多数派からの偽りの合意」を受けているという性質を持つことから「偽の合意効果」とも呼ばれています。いわゆる「暗黙の了解」なんかもこの効果に当てはまります。
《フォールコンセンサス効果の例》
- 上座にはいつでも自分より目上の人が座るべき(日本人特有)
- 待ち合わせ場所には5分前には遅くても到着しているべき
- 仕事を辞めるときは顔を合わせて直接伝えるべき
- 今の時代、定職につかないのが当たり前
- 国や地域によって変わる美人の定義
- 宗教などで行われている慣例行事
など。
参考記事:フォールコンセンサス効果
気分一致 効果
「気分一致効果」とは、「気分がいいときは物事のいい面がよく見え、気分が悪いときは物事の悪い側面が見えやすくなる」心理効果のこと。
気分によってものの見方や感じ方が左右されます。
《気分一致効果の例》
- 寝不足のとき不安なことばかり頭に浮かぶ
- 落ち込んでいるとき嫌なことばかり思い出す
- 調子がいいときリスクを恐れずにどんどん行動できる
- 嬉しいことが起きたとき自分に自信がつく
自己成就予言
「自己成就予言効果」とは、「根拠のない噂や思い込みであっても、その状況が起こることを想定して行動してしまう心理現象」のことです。
《自己成就予言効果の例》
- どうせ失敗すると考えていたら本当に悪い結果になった
- 災害時の根拠のない噂による物の買い占め(トイレットペーパーの買い占めなど)
参考記事:自己成就予言効果
スポットライト 効果
「スポットライト効果」とは、「他人からの自分に対する評価を実際以上に気にしすぎてしまう心理効果」のこと。
《スポットライト効果の例》
- 歌詞を間違えたと思って歌っていたら誰も気づいていなかった
- めっちゃ緊張していたのに
参考記事:スポットライト効果
プラシーボ 効果
「プラシーボ効果」とは、「有効成分が含まれていないにもかかわらず、治療効果が表れる」こと。 反対に、副作用が表れる現象を「ノシーボ効果」といいます。
《プラシーボ効果の例》
- すごく評価が高かったから買ってみたけど、本当にすぐに効いてきた(かも)
参考記事:プラシーボ効果
サンクコスト 効果
「サンクコスト効果」とは、明らかに不要なものとわかっているにもかかわらず「何らかのコストを支払ったものを容易に手放せなくなる効果」のことをいいます。
↓記事の後半で解説しております。
保有効果
「保有効果」とは、「手に入れた際のコストよりも手放す際の価値の方が大きく感じられ、手放したくなくなる心理効果」のことです。 つまり、「手放すのはもったいない!」という心理が働くことを言います。
- お気に入りの車の買い替え
- 全巻揃えたマンガの売却
- 苦労して集めたコレクション
など。
参考記事:保有効果
寛大効果
「寛大効果」とは、「相手の長所は過大評価されやすく、短所は過小評価されやすくなる心理効果」のことです。 つまり、人は「良い面ばかり見て、悪い面には目をつぶる」傾向にあるということです。
《寛大効果の例》
- あの人はたまにミスはするがそれは誰にでもあることだ
- 普段冷たいけど、たまに優しくて実は物凄くいい人だ(DVなど)
- 私の娘は美人で優しくて賢い、完璧な娘だ(いわゆる親バカ)
参考記事:寛大効果
特に気をつけたい 心理効果 バイアス 3選
さて、まずはバイアスに関わる心理効果の一覧を見ていただきました。
そしてここからは、筆者が選ぶ、特に気をつけたいバイアスの心理効果をご紹介いていきます。
バイアス 1:計画錯誤
カナダのウルフレッド・ローリエ大学のロジャー・ビューラーは非常にシンプルで画期的な研究を行いました。 まず彼は学生たちにある重要な論文を提出できそうな期限を答えさせました。すると学生たちの半数近くが、締め切りの10日前には提出できると回答しました。 しかし実際には締め切りの1日前にようやく書き終えたという学生がほとんどだったことがわかりました。 研究によると人は計画にかかる時間を甘く見積もる傾向があり、これを心理学の用語で「計画錯誤」と呼んでいます。
「全ての計画を狂わせる「計画錯誤」の罠とそれの解決策とは!?」より引用
認知心理学者の「ダニエル・カーネマン」が命名。
計画を立てる際、ベストな予測を元にされやすいバイアスのこと。
目標達成に必要な時間や予算などの予測は過小評価されやすく、実行や達成の容易さの予想は過大評価されやすい。
この計画錯誤というバイアスが起こることによって、計画を立てたときは「余裕!」と思っていたのに、実際やってみたら「いつまでも終わらない!」という現象が起こります。
《計画錯誤の例》
- レポートなどの課題をこなすとき、2週間あれば終わらせられると思って計画を立てていたら、実際に完了まで4週間かかった。
- 2万円あれば一か月の食費は足りるだろうと思っていたら、実際には3万円以上かかった。
- 30分あれば目的地にたどり着けるだろうと思っていたら、50分以上かかって到着した。 など。
《計画錯誤への対策》
1.タスクノルマを細かく分類する
まずは目標を達成させるために必要なノルマをはっきりさせていきます。
「計画錯誤」が起こる原因のひとつに「やるべきことが不明瞭」である場合があるからです。
必要なノルマを想定したら、そしてさらに、そのノルマに対するタスクを決めていきます。
ここまでは計画を立てる際に普通にやっていることだと思います。
そしてさらに、そこから1週間でできるタスク、1日でできるタスク、1時間でできるタスク、10分でできるタスク、1分でできるタスクと、所要時間ごとにできるタスクを階層として分けていきます。
所要時間ごとに細かくタスクを設定するメリットは2つあります。
- 大、中、小とタスクの規模が選り分けられる
- ノルマ達成までのロードマップが自然にできあがる
例えば、「YouTube登録者1000人」を目指す場合
「必要だと思われるタスク」
- 良質な動画コンテンツを増やす
- TwitterなどのSNSのファンも増やしてどんどん発信する
- イベントを企画してコラボ相手を見つける
など。
→「良質なコンテンツを増やすためには」
(活動のジャンルによって変わりますので一例としてあげています)
「1分でできること」
- 企画アイディアを1つ考える
- カメラを設置する
- パソコンを起動させる
など
「10分でできること」
- 動画の構成を考える
- バズってる動画をリサーチする
- 撮影で使うものの用意
- 動画のロケーションを決める
- シーンごとの撮影
など
「1時間でできること」
- 動画の不要な部分をカット編集する
- サムネイル作成
- テロップなどの編集
- 動画で使うものの下準備
など
「1日でできること」
- 動画投稿
- バズっている動画の分析
など
「1週間でできること」
- 企画の準備(買い出しなど)
- 小規模企画(撮影が15分以内で終わる動画)4本、中規模企画(撮影が15〜30分で終わる動画)1本の投稿
など
どうでしょうか?
「所要時間」を考えて階層に分けるだけで、計画の骨組みがしっかりしてきたように感じませんか。
「やるべき行動がイメージできる」というのが集中力を高め、計画の達成率を高めてくれます。
2.なんでも1.5倍で考える
単純に、計画を立てた際の数値で表されるノルマを1.5倍にします。
- 移動時間が1時間かかりそうなら、時間設定を1.5時間にする。
- デートの費用が1万円ぐらいかかりそうなら1.5万円用意する。
- 30日くらいかかりそうなら45日までかかることを想定する。
など。
1.5倍にしたのは、第一に計算がしやすいこととと、第二に2倍では余裕ができすぎて気が緩む可能性が高まるからです。
「1と、+0.5は保険」くらいに考えれば心に余裕ができつつ、かつ、気が緩み過ぎることもないと思います。
たとえば、「一日で終わらせられる(はずの)ノルマなのに、もう一日あるから余裕」と考えたら、前半の一日をダラダラ過ごしてしまいそうですが、「期限が明日の午前中まで」となればどうでしょう。
「明日の午前中までだと明日はそんなにいろいろできないな」と制限時間がイメージでき、+0.5の部分がより「予備」として捉えられるのではないでしょうか。
さらに別の角度から考えれば、実質「期限が2段階になる」ということでもあります。
つまり、最終目標の内側に理想目標ができるイメージです。
1個目の期限を想定して動くことで、行動の余白を減らす必要性ができてくるので、1段階だけの期限よりも無駄な時間の削減にもつながります。
3.他の人の失敗例を分析する
やはり世の中に出ている実例を参考にすることはとても有意義なことです。
「失敗する可能性があること」を前提に考えられることによって、計画の落とし穴に事前に気づきやすくなります。
また、他人の体験談を聞くというのも大切です。
「体験談を聞く」ということは同時に「計画に対する意見を聞くこと」につながります。
もちろん、失敗例は他人だけでなく、過去の自分の体験から振り返るのも有効です。
注意して欲しいのは、「他人のことだから自分には当てはまらない」と考えるのではなく、ここでは「客観的な事実」をもとに行動を予測することが大切です。
他に客観視するためには「他人に計画をチェックしてもらう」というのも有効です。
4.最悪の状態を考える
「計画錯誤」のそもそもの原因は「常に最高のコンディションであること」を想定した上で計画が立てられていることにあります。
そこでシンプルに「最悪な状態でもできるだろうか?」ということをもとに、自分の立てた計画を再確認することが大切です。
「最悪な状態でもできること」を考えることで、自然にノルマへのハードルも下がり、余分なタスクを削るという発想も持ちやすくなります。
その結果、ノルマ達成もしやすくなり、計画倒れも起こりづらくさせることができます。
バイアス 2:サンクコスト効果
サンクコスト効果とは、これまで投資してきたお金や労力(埋没費用)をもったいなく感じ、回収しようと躍起になるあまり、合理的な判断ができなくなってしまうこと。「コンコルド効果」とも呼ばれるものです。 「サンクコスト効果とは? 回避&活用方法を徹底解説!」より引用
サンクコスト効果とは、簡単に言うと「もったいないからやめられない!(手放せない)」と思い込むことによって引き起こされるバイアスのことです。
《サンクコスト効果の例》
- 多額を課金したため、途中でやめられず当たるまでガチャに課金するようになった。
- 年会費を払っているサブスクを他のコンテンツに乗り換えることができない。
- 長い期間、着ていないにもかかわらず服がなかなか捨てられない。
- 映画館の映画で、つまらないと途中で気づいても最後まで見続ける。
- もう使う機会もなく、長い期間使っていないはずの過去のファイルや書類を整理できない。
- 株の塩づけ(損切ができず下落した株を保持し続けること)。
《サンクコスト効果への対策》
1.機会損失を考える。
機会損失とは簡単に言えば「新しいチャンスを逃すこと」です。
つまり、「新しいことをするための時間を失う」ということでもあります。
「損だとわかっていながらそれを続けること」によって起こる、他への悪影響を考えることで「それを手放す意識」を高めることができます。
たとえば、「これにかける費用があれば、別のことに使える」「これにかける時間があれば、○○ができたのに」などです。
2.保持を続けるルールを決める。
もっと具体的に言えば、「かける時間と費用」に上限を設けます。
上限の基準は「取り返しのつかなくなる限界値のだいたい半分くらいまで」にするのがおすすめです。
たとえば、「弁護士になる」という目標があったとしましょう。
「何歳になろうとも絶対なる!」という固い決意のもと、人生最大の目標に掲げ何度落ち続けても司法試験に合格し続けるまでやり続ける! という話はまずはおいておいて、ここではもっとドライに、物理的に考えていきます。
自分にとって取り返しのつかなくなる限界値が「35歳」だとします。 (※実際には司法試験予備試験に合格した後の最初の4月1日から5年の間に受験できる回数は5回までで、それ以降は再度司法試験予備試験に合格する必要があるという上限が存在します)
そして、今が仮に22歳だとしたら35歳までは13年あるので、その半分の6.5年、つまり28歳の半ばまでが上限になります。
なぜ上限の半分なのか? と言われたら、失敗を水に流せる余裕があるからです。
過半数を超えると、次第に焦りが生まれ、「あとには引き返せない感」が次第に強くなっていきます。
さらには、「ここまで損したら、いかなる状況でもやめる」という上限を設けることで、「まだ大丈夫」という考え自体を否定することができます。
「まだ、ちょっとだけなら大丈夫!」→「いやいや、ルールを破ってこれ以上やると何もできなくなる(つまり機会損失が起こる)」
と考えることが大切です。
3.失敗を他に利用できないか考える。
サンクコスト効果に陥る原因の最たるものは「もったいない」と思うことです。
「今までのことがすべて無駄になる」と考えることで執着心が芽生えてしまうので、他への使い道を考え無駄にしないようにすることで「もったいない」という気持ちを取り除くことができます。
たとえば、よく耳にする「失敗を次に活かす」というのは何にでも使えるとても有効な考え方です。
4.「今がまったくのゼロの状態だったらどうするか」を考える。
「今までかけてきた時間や費用」が頭から離れないことで、合理的な判断ができなくなるのであれば、一度問題から離れ客観的に状況を分析する必要があります。
そこで有効なのが、「時間も費用も全くかけていない他者」になりきることです。
つまり、「まったくゼロの状態から状況を考え直す」ということで、それを見つめていくうちに「損するためにわざわざかける人はいない」と感じることができたら成功です。
「ゼロから考えるなんてできない」という人は、代わりに「第三者に意見を聞いてみる」というのも有効です。
とにかく、「客観視して状況を分析できるようになること」こそが、サンクコスト効果から抜け出すポイントになります。
参考記事:サンクコストとコンコルド効果|損失が拡大するもったいない心理とは
バイアス 3:透明性の錯覚
自分の考えていることや感じていることが、実際以上に他者に伝わっていると考える傾向を透明性の錯覚と言います。 つまり、本来ならば他者からは見えないはずの自分の内的経験が、他者に見抜かれている程度を過大評価していると言えます。 このような透明性の錯覚は、本人が隠そうと思っていない内容であっても、同じように生じます。 「透明性の錯覚illusion of transparency」より引用
透明性の錯覚とは、簡単にいうと「言わなくても相手に伝わるだろう」と考えるバイアスのことです。
つまり、相手は自分のことをよく知っていて、自分の考えはつつぬけになっていると感じることでもあります。
《透明性の錯覚の例》
- めちゃくちゃ緊張した歌のステージだったけど、友達には「全然緊張してなくてすごい」と褒められた。
- 「言わなくても察してやってくれているだろう」と思っていたら結局、何もやってくれていなかった。
- 「印象悪くて絶対落ちたな」と思っていた面接に、実は高評価で受かっていた。
など。
《透明性の錯覚への対策》
1.「透明性の錯覚」があることを自覚する
つまり、「心を完全に読み取れる人はこの世に存在しないこと」を意識することでもあります。
ある実験で、「嘘つきがまぎれているグループ」で話し合いをしてもらい、誰が嘘つきを当てるという実験を行った際、嘘をついた人は「参加者の50%近くの人にバレている」と回答したが、実際には25%くらいの人にしかバレていなかった。という結果があります。
まぁ『人狼』というゲームが成立するぐらいですから、他人の心を読む難しさはうなずけますね。
2.感情表現をしっかりする
つまり、「気持ちは口に出さなきゃ伝わらない」ことを前提に人と関わることでもあります。
たまに、「言われなくてもわかっている」と言われることもあるかもしれませんが、「伝わらないことで誤解が生じるリスク」の方が損失が大きいということが考えられれば気にする必要はないでしょう。
たとえ相手が小学生でも伝わるように話すこと、が大切です。
3.不安や緊張に強くなる
そもそもこの「透明性の錯覚」というのは、「相手に心を読まれていたらどうしよう」という不安や緊張が原因になっています。
なので、不安や緊張対策をしてメンタルを安定させておくことが有効です。
対策については、過去に記事にしていますのでそちらを参考にしてみてください。
4.スピーチの動画にとり、その動画を翌朝見返して感情を分析してみる
つまりは、客観視することが大切です。
「自分が思っているほど感情は表に出ていない」ことを知ることで、「気持ちや感情を伝える大切さ」を意識することができるようになります。
他にはやはり「他の人に自分の印象を聞く」というのも客観視するためには有効な手段です。
《参考記事》
- 参考記事:計画錯誤とは 〜将来の自分への責任転嫁〜
- 参考記事:サンクコストとコンコルド効果|損失が拡大するもったいない心理とは
- 参考記事:情報伝達の錯覚(1)
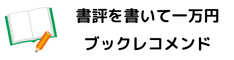


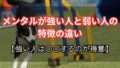

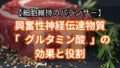
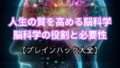



コメント